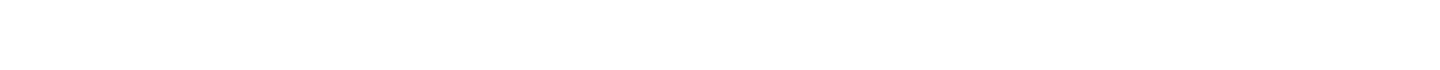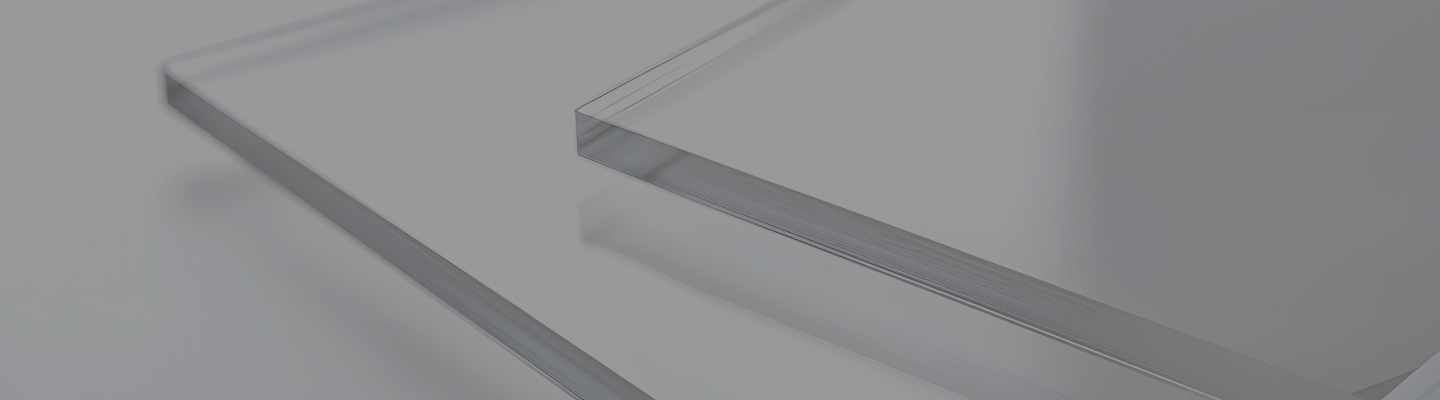陸上養殖のメリット・デメリットは?養殖業界の現状も詳しく解説
陸上養殖は、陸上の設備で計画的に魚介類を育てる方式です。水質や水温を管理できるため安定供給が可能になる一方で、初期投資や運用コストの高さが課題とされています。
この記事では、陸上養殖のメリット・デメリット、さらに養殖業界の現状についても詳しく解説します。
陸上養殖を検討している方や導入するか迷っている方は、ぜひ最後までご覧ください。
陸上養殖とは

陸上養殖とは、海ではなく陸地に設置した水槽やプールを利用して魚介類を育てる方法です。水温や酸素量、水質などを人の手で調整し、種類ごとに適した環境をつくることで新鮮な魚を育てられます。
海の環境に大きく左右される海面養殖に対し、陸上養殖は天候や海流の影響を受けにくい点が大きな特徴です。
陸上養殖についてもっと詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。
陸上養殖のメリット

陸上養殖は、これまでの海面養殖とは異なる方法として注目され、水産業の新しい可能性を広げています。
自然環境に左右されにくく、より計画的に運営できるため、各地で導入や研究が進められている養殖方法です。ここでは、陸上養殖ならではのメリットを詳しく紹介します。
自然環境の影響を受けにくい
陸上養殖の閉鎖循環式では、一度使用した水を濾過や殺菌によって浄化し、再び水槽に戻して使う仕組みを採用しています。
そのため、雨・気温・海流などの影響を受けにくく、安定した飼育が可能です。さらに、水温調整設備によって魚に適した温度を維持でき、塩分濃度を調整して生育期間を早めることもできます。
陸上養殖は計画的な生産が実現できるほか、従来の漁業のように漁船や漁具を多用する必要がないため、作業効率の向上にもつながります。
寄生虫の繁殖を抑制しやすい
寄生虫の繁殖を抑えやすいのも、陸上養殖のメリットです。海面養殖では網で仕切って魚を育てるため、外部の海水から寄生虫が侵入する可能性があります。
一方、閉鎖循環式の陸上養殖では海や川の水を使用せず、施設内で浄化された水を循環させるため寄生虫の侵入リスクを大幅に減らすことが可能です。
輸送コストを削減できる
陸上養殖は設置場所を選ばず、海辺だけでなく内陸部や都市部でも導入できます。消費地に近い場所で養殖を行うことができるため、輸送距離を短縮でき、人件費や物流コストの削減にもつながります。
また、生産地と消費地が近いことで、消費者には鮮度の高い魚を手頃な価格で届けやすくなるのも大きなメリットです。さらに、多様な魚種に対応できる点も事業者にとって魅力のひとつです。
生産性の向上
陸上養殖では、水温や給餌の管理を人の手で行えるため、生産効率の向上が見込めます。たとえば、水槽内の温度を魚介類に適した状態で保つことで成長が早まり、養殖にかかる期間を短縮できます。
さらに、餌の量や与えるタイミングを細かく調整できるため、無駄を減らしながら計画的な育成が可能です。これにより、市場の需要に合わせて柔軟に出荷時期を調整でき、供給を安定させられます。
環境への負担が少ない
陸上養殖の閉鎖循環式では、水を浄化して繰り返し利用する仕組みを取り入れているため、魚の排泄物や食べ残しなどを含んだ汚水を海や川に流しません。
そのため、周囲の環境に余計な負担をかけずに養殖を続けることができ、より持続可能な方法として注目されています。
また、海や川といった自然の場所を使用しないので、野生の魚や貝などへの影響も抑えられます。さらに、魚が外に逃げ出す心配もないため、自然の生態系を乱すリスクも最小限にとどめられるのもポイントです。
陸上養殖のデメリット

陸上養殖には多くの利点がある一方で、注意すべき課題も存在します。導入や運営にあたっては思わぬ負担やリスクが伴うこともあり、事前に理解しておくことが欠かせません。
ここでは、代表的なデメリットについて紹介します。
設備導入費が大きい
陸上養殖のデメリットは、導入時にかかる費用の高さです。養殖を行うためには、水槽や濾過装置、殺菌装置など多くの設備をそろえなければなりません。
また、土地を持っていなければ、新たに場所を確保する費用も加わります。さらに、養殖環境を維持するには水の循環や温度調整に大量の電力が必要となるため、電気代などの運営コストも継続的に発生します。
専門的な知識や技術が必要
陸上養殖で新鮮な魚を育てるためには、専門的な知識や技術が欠かせません。魚を健康に保つには水温・酸素量・pH・窒素などのバランスを正しく管理する必要があります。
知識や経験が足りないと水質の悪化や酸素不足、病気の発生につながりやすく、最悪の場合は多くの魚が死んでしまうこともあります。そうなると大きな経済的損失を招く恐れがあるため、正しい知識と管理が重要です。
アクア丸善では、知識がない方でも養殖できるようにサポートいたします!
病気の発生や拡大のリスク
陸上養殖は限られた水槽の中で魚を育てるため、ウイルスや病気が入り込むと一気に広がり、大きな被害をもたらす可能性があります。
特に細菌やウイルス、寄生虫による病気に弱い魚の場合は、使用できる薬が限られているので注意が必要です。病気を発生させないように、日ごろから水槽の衛生管理をしっかり行うことが大切です。
災害による被害のリスク
陸上養殖は多くの機械を使用するため、故障や停電などのトラブルで大きな被害が出る恐れがあります。
循環装置や温度管理システムが止まったり、水害で設備が壊れたりすると、魚が全滅する可能性もあります。そのため、非常用発電機を備えるなど、災害に備えた対策が必要です。
陸上養殖の現状

現在、陸上養殖の施設は全国で少しずつ増え続けています。水産庁によると、令和7年1月時点で届け出件数は740件に達し、特に沖縄県や九州地方で多くの養殖場が確認されています。
養殖種別では、クビレズタ(海ぶどう)・ヒラメ・クルマエビが上位を占め、海水魚や海藻を陸上で育てる取り組みがさまざまな地域に広がっている状況です。
養殖が行われていなかった都道府県でも新規参入が見られるようになり、サケ・マス類も件数が増加しています。
ヒラメ
ヒラメはあまり動かないので、必要とする酸素量が少ない魚です。生育に適した水温が18〜24℃と安定しているため、最近では陸上養殖で育てられることが多くなっています。
サーモン
サーモンは、他の魚に比べて環境への負担が少ないのが特徴です。WWFジャパンの前川聡氏は「1キログラムのマグロを育てる場合は餌が10〜15キログラム必要だが、サーモンは1〜2キログラムの餌で育成できる」と説明しており、効率の高さから環境にやさしい魚として注目されています。
さらに、サーモンはDHAを豊富に含んでいるため健康志向の人々に人気があり、世界的にも需要が年々増え続けています。
参照:東洋経済
まとめ
陸上養殖は、天候や海流の影響を受けにくく、計画的な生産が可能な養殖方法です。寄生虫対策や環境への負担軽減、輸送コスト削減など、多くのメリットがあります。
一方で設備投資や運営費の高さ、専門知識の必要性、病気や災害によるリスクといった課題も抱えています。
こうした利点と課題を踏まえ、現場では実績とノウハウを持つ専門企業の存在が重要です。
アクア丸善は、「いけす・陸上養殖設備」の設計・製造・施工を一貫して手掛けています。耐久性・透明度・耐水性に優れたアクリルやFRPを採用しているため、陸上養殖の過酷な環境下でも長時間にわたり安定して使用できるのが特徴です。
また、いけすの形状やサイズなど、施設環境や養殖対象に合わせた完全カスタマイズ設計を行っています。
陸上養殖を検討している方や養殖業界へ新規参入したい方は、ぜひアクア丸善にお問い合わせください。
お問い合わせはこちら