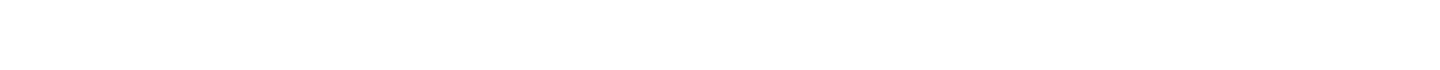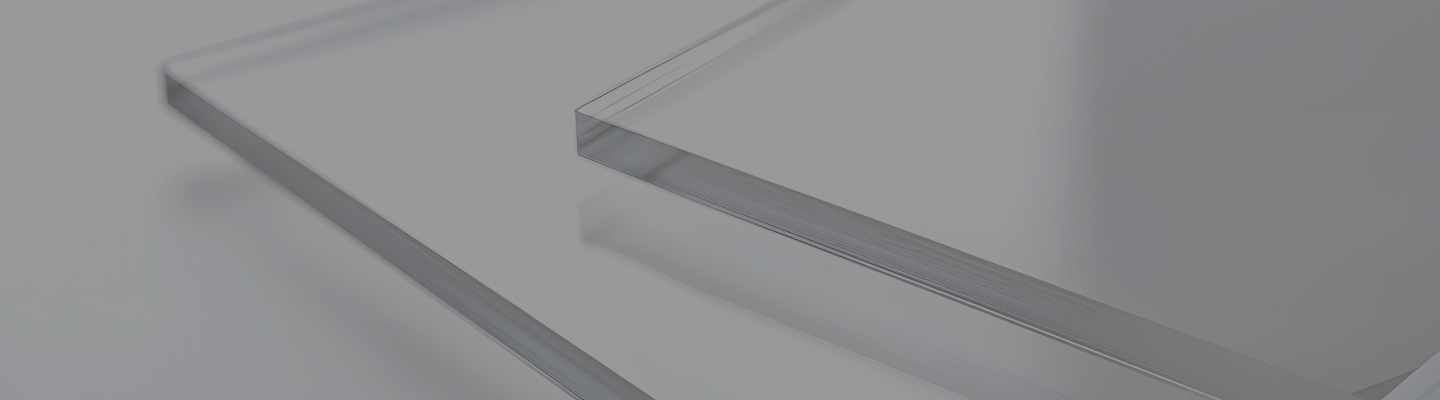陸上養殖とは?種類や必要な設備、期待できる効果を詳しく解説
近年注目を集める陸上養殖は、都市部や内陸でも新鮮な魚を育てられる点が特徴です。天候や海流に左右されにくく計画的な運営が可能なため、新たな水産業の形として広がりつつあります。
この記事では、陸上養殖の仕組みや方式の違い、導入に必要な設備、さらに期待される効果を解説します。
陸上養殖について知りたい方や陸上養殖を始めようと検討している方は、ぜひ最後までご覧ください。
陸上養殖とは

陸上養殖とは、陸上に設けた水槽やプールなどの設備で魚介類を育てる方法です。水質・水温・酸素量を人工的に管理し、魚ごとに適した環境を整えることで、新鮮な魚を安定して養殖できます。
海の状況に左右される海面養殖と異なり、天候や海流の影響を受けにくいため、計画的に生産できるのが大きな特徴です。
陸上養殖が注目される理由
陸上養殖が注目されている背景には、国内の漁業・養殖業の生産量が長期的に減少していることにあります。農林水産省の調査によると、生産量は1984年をピークに下がり続け、2021年には約421万トンまで落ち込みました。
その要因として、漁業従事者の減少や海洋環境の変化があり、安定した供給が難しくなっている点が挙げられます。こうした状況を踏まえ、海の影響を受けず効率的に魚を育てられる新たな手段として期待されているのが陸上養殖です。
実際に海面養殖の事業者は減少傾向にある一方で、陸上養殖への事業参入は2016年以降増加しており、拡大が進んでいます。
参照:水産庁 栽培養殖課「令和4年度 陸上養殖実態調査委託事業の結果概要」
陸上養殖の種類
陸上養殖には、水の使い方や管理方法の違いによって、いくつかの方式があります。水を常に入れ替える方法や装置を使って再利用する方法、さらにその中間的な仕組みを採用する方法など、それぞれに特徴とメリット・デメリットがあります。
魚を健康に育てるためには水質管理が欠かせません。方式によって養殖の環境やコストが変わるため、目的に応じて選択することが大切です。ここでは、代表的な3つの方式を紹介します。
かけ流し式
かけ流し式は、海や川からポンプで新しい水をくみ入れ、古くなった飼育水をそのまま排出する方式です。
基本的には、水槽と給排水用ポンプがあれば運用できるため、設備投資を抑えやすい点が特徴です。また、環境によっては常に新鮮な水を取り入れられるため、生育に適した条件を維持しやすいメリットがあります。
一方で、自然水を利用するため水質の変動に影響を受けやすく、安定した管理が難しいという課題もあります。
閉鎖循環式
閉鎖循環式は、海や川から分離された陸上の水槽やプールで魚介類を育てる方法です。使用した水はそのまま捨てず、濾過装置や殺菌装置で浄化して再利用します。
常に水を入れ替える必要がないため、天候や海の環境変化の影響を受けにくく、水質を安定して保てるのが大きな利点です。また、水温や酸素量を細かく調整できるため、多様な魚種の養殖に対応できます。
その反面、かけ流し式に比べて必要な設備が多く、導入や運営のコストが高くなるのが懸念点です。さらに、装置に汚れが溜まりやすいため、定期的な清掃やメンテナンスも欠かせません。
半閉鎖循環式
半閉鎖循環式は、かけ流し式と閉鎖循環式を組み合わせた養殖方法です。新しい海水や河川水をポンプで取り込みながら、使用済みの飼育水の一部を濾過・殺菌して再利用します。
この仕組みによって、水質を一定に保ちつつ排水量を減らせるため、効率的で環境への負担も抑えやすいのがメリットです。
ただし、古い水を一時的に溜める設備や排水処理の仕組みが必要となるので、導入や維持にはコストがかかります。
陸上養殖がもたらす効果

陸上養殖は、これまで海や川に依存してきた養殖のあり方を大きく変える新しい手法として注目されています。
水温や酸素量を管理して効率的に魚を育てられるだけでなく、自然環境への負担を抑えやすいのも特徴です。ここでは、陸上養殖がもたらす効果を詳しく解説します。
生産力がアップする
陸上養殖では水温や酸素量などの環境を人の手で調整できるため、魚種によっては生産効率を高めることが可能です。
国内ではヒラメやサクラマス、クエといった多様な生き物を対象に実験が行われており、事業として成立させるための方法が検討されています。
さらに近年は水質を自動で管理できるツールや、AIによる飼育サポートシステムも導入されるようになり、生産性の向上を後押ししています。
参考:オプテックス株式会社 陸上養殖の普及に欠かせない水質管理のDX化
リージョナルフィッシュ株式会社 世界的に注目されている陸上養殖。課題は採算性。
環境への影響を低減できる
陸上養殖は、自然環境に与える影響を小さくできる養殖方法です。閉鎖循環式では、水槽内で汚れた水を浄化して繰り返し利用するため、汚染水を海や川に流しません。
さらに、魚が逃げ出す心配もないので、自然の生態系を乱すリスクも軽減されます。こうした仕組みによって海の環境を守りやすくなり、結果的に漁業や海面養殖にもプラスの効果をもたらすと期待されています。
輸送・流通コストを削減できる
陸上養殖は、海から離れた地域や市街地でも設備を設置して運営できるため、人件費や輸送コストを削減できるのが大きな利点です。
生産地と消費地を近づけられることで、消費者には新鮮な魚をより手頃な価格で届けやすくなります。多様な魚種を扱える点も、事業者にとって魅力のひとつです。
陸上養殖で欠かせない設備

陸上養殖を安定して行うためには、魚介類の生育環境を守る多様な設備が必要不可欠です。水槽はもちろん、水質を清浄に保つ濾過装置や酸素供給を助ける循環ポンプなどにより、魚介類が快適で安全な環境が整います。
ここでは、高い生産性を実現するために重要な設備を詳しく紹介します。
水槽
養殖において水槽は、魚介類を安全に収容して育てるために欠かせない設備です。水槽には材質や形状にさまざまな種類があるため、飼育する魚や貝などの特性に合わせて選ぶことが大切です。
また、設置する場所との相性やゴミや汚れが溜まりにくい形を選ぶのも、管理をしやすくするために重要なポイントとなります。
濾過装置
濾過装置は、水槽内の食べ残しや排泄物、バクテリアなどの汚れを取り除くための設備です。方式には開放式循環濾過と閉鎖式循環濾過があり、処理の考え方としては物理濾過と生物濾過があります。
開放式循環濾過
開放式循環濾過は、一番低い貯水槽からポンプで水を一番高い高架水槽へ上げます。高低差で水を流して開放された濾過槽を経由し、再び貯水槽に戻る仕組みです。
水は空気に触れながら濾過材を通過するため、「重力式循環濾過」とも呼びます。
閉鎖式循環濾過
閉鎖式循環濾過は、密閉した濾過槽に貯水槽の水をポンプで送り、濾過した水が水槽を経由して貯水槽に戻ります。
配管から濾過までが密閉状態で進むため、水は空気に触れません。ポンプの圧力で循環させる方式なので、「圧力式循環濾過」とも呼ばれています。
物理濾過
物理濾過は、水槽内に溜まる食べ残しや排泄物などのゴミを取り除くために欠かせません。ゴミの種類によって処理の仕方が変わるため、濾過装置の仕組みを理解しておくことが大切です。
また、こまめなメンテナンスが必要になるので、導入前には性能や扱いやすさを確認することが求められます。
生物濾過
生物濾過は、水槽内に含まれる汚染物質を微生物が分解し、水をきれいに保つ役割があります。導入する際は微生物が住みつきやすく、水がしっかり循環できるように十分な表面積を持つ素材を選ぶことがポイントです。
循環ポンプ
水槽の水は濾過槽などの設備に送るために、常に循環させる必要があります。その役割を担うのが循環ポンプで、種類によって水の流量が異なるため、飼育する魚介類に合ったものを選びましょう。
殺菌装置
水槽内の病原菌やウイルス対策には、殺菌装置が不可欠です。単独で使うよりも物理・生物濾過などの濾過設備と適切に組み合わせることで、水質を安定させられます。
ただし、飼育生物に合わないと健康被害が出る恐れがあるため、濾過設備を慎重に選ぶ必要があります。
水温調節機
養殖では、水槽内の水温を常に適切に保つことが重要です。水温調節機は導入コストがかかりますが、断熱性の高い水槽と組み合わせると効率よく温度管理ができます。
まとめ
陸上養殖は、海の影響を受けずに水質や水温を管理しながら、魚介類を効率的に育てられる新しい手法です。
方式にはかけ流し式・閉鎖循環式・半閉鎖循環式があり、それぞれに特徴やコスト面での違いがあります。
また、水槽・濾過装置・殺菌装置・水温調節機などの設備を整えることで、生産性の向上や環境負荷の軽減、輸送コストの削減といった効果が期待できます。そのため、次世代の養殖方法として重要な役割を担う存在です。
アクア丸善では、陸上養殖設備・いけす・水のカーテン・演出水槽・アクリル加工・滝・池などの特殊製品を製造しています。
設計から自社製造、設置まで一貫して対応しており、全国で10,000件以上の施工実績があります。
陸上養殖を始めようと検討している方は、ぜひ一度アクア丸善にご相談ください。
お問い合わせは、こちら